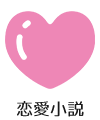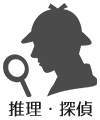方言放談-2
父親が教職員だったせいかもしれない。
小学生時代の我が家の書棚には、小学生の詩や作文の「優秀作」選集がいろいろとあった。
これを読んで、お前もこれに掲載されるくらい良い文章を書け、なんて圧力は感じなかったから楽しく読んでいた。
━──━
女子生徒が書いた作文のなかに、家族みんなでデパートに行ったってのがあった。
デパートの大食堂で昼食にしたのだけど、混雑していて注文してもなかなか品物が来ない。
お子さまランチをたのんだ小さな弟が、たまりかねてこう言った。
「こんだかやあ、こんだかやあ。」
注釈がなかったけど、どうも「(まだ)こないのか」と言う意味の方言だろう。
この言葉が自分も父親も気にいって、食堂で注文した品物がなかなかこないとつい二人で、
「こんだかやあ、こんだかやあ。」
と、合唱(?)していた。
この作文の作者のデータはわからないけど、訪ねたデパートが「まるみつ」だったから、宮城県の子だったのかなぁ。
─━━─
女子生徒の作文で、母親がバリカンを手に兄に散髪をしたってのがあった。
当然のことながら、散髪に慣れない母親がとんでもない髪型にしてしまう。
鏡でその惨状を見た兄は結局散髪屋に行くことになり、母親にこう言って出てゆく。
「もう、わがえでは、つまんど。」
この方言には「もう、うち(=自宅)では(髪を)刈ってもらわないよ。」と編注がついていた。
この作者のデータを全く覚えてないが、だいぶん時を経てから思いがけないことを知った。
髪を刈ることを「髪を摘(つ)む」と言う言い方は、方言というよりむしろ「古い言いまわし」になる……と。
自分がガキのころ、いい年齢したひとが「弁当をつかう」と言うのを聞いて(弁当は「たべる」ものじゃないのか)と思っていた。
その「弁当をつかう」は方言だと思ってた。
ところがだいぶ経って高見順の『敗戦日記』を読むと、
……私たちは(東京の)国際通りに再び戻った。通りに近いところに「弁当を使う方にはお茶があります」という紙の出してある店があったことを私は覚えていた……
(2月13日の記述から)
ここをはじめ「弁当をつかう」という文章がいくつもあった。
「弁当をつかう」も、単に古い言いまわしだったのだ。